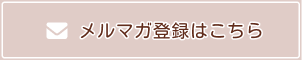お役立ち情報INFORMATION
-

2025.02.06
言葉の発達5段階
https://youtu.be/DTXTk3P-GZ8
-

2024.12.20
食事中に離席する への発達支援
嬉しいご報告、結果です。 食事中に離席して困っていたケースです。 【支援】 ・離席しようとしたら「ごちそうさまなのね」と確認しあいさつさせる ・ごちそうさまではない場合は座ってもらい、喜ぶ 「そうなんだね、座っていただきましょう」「座れて素敵ね」など ・離席する場合には「ごちそうさま」をさせて、ご飯を片付けさせる ※ここが重要です。 しれーっとご飯がなくなるのが大事、そのあとも【ない】のが大事です! 今食べなければ、【ない】が大事なのです。 心苦しいですが、してくださいね! https://youtu.be/Dmvqn_cpMXo 【経過】 だんだんと離席しなくなってきた。 1か月したら、離籍しないし、片づけも身に付いて一石二鳥。 親御さんは喜んでいます。 【ポイント】 親の信念が大事です! 曲げないでください。 https://youtu.be/-g5ZK1CEIwQ
-

2024.12.20
人の気持ちを理解する支援 ①ことばの実況中継
インフルエンザで倒れておりました。 皆様もお気をつけください。 さて、今日はことばの実況中継についてです。 なぜ実況中継なのか 言葉というものは、人から学ぶものです。 言葉は、人からかけられなければ学びません。 気持ちの言葉も、もちろん同じ。 気持ちを理解する、気持ちのコントロールの件でいえば ☆相手の気持ちを理解するには自分の気持ちの言葉が必要 ☆自分の体験していない気持ちは理解できない ☆言葉になっていない気持ちはコントロールできない というわけなので 気持ちを言葉にすることが大事なわけですよね。 そのためには、言葉を抱えることが必要 つまり、言葉にして実況中継をしていくことが必要なわけです。 とくに、自分が感じている気持ちを言葉にしてもらわないと 気持ちの言葉は学べません。 どうやってするの? 簡単です!以下の3つをすればいいだけです。 ☆子どもがしていることを言語化 ☆子どもが感じている気持ちを翻訳して言語化 ☆こちらの気持ちを言語化 だけです! ただ、子どもが感じていることが【わからない】ことが多いようです。 その場合には、細井に聞いてください。 動画も見て、参考にしてくださいね。 https://youtu.be/dd4E5Ibr5PY なんでも相談、体験でお待ちしております!
-

2024.12.15
人の気持ちを理解するには
人の気持ちがわからない・・・ が結構コミュニケーションでの悩みで多い気がします。 子どもさんが相手の気持ちをわからない場合、 以下の原因があるかも。 ①自分の気持ちがつかめていない(未整理) 自分が感じたことのない気持ちはわかりません。 気持ちが未整理でモヤモヤしている場合には 相手の気持ちはわかりません。 ②相手を映して感じられない 相手のまねができないと、人の気持ちがわかりません。 なぜなら、人は相手の身体つきをまねして写し取って 相手の気持ちを知るからです。 ③反応の仕方がわからない 気持ちをなんとなくわかったとしても どのように表したらいいか、反応したらいいか わからない場合があります。 経験不足ですね。 というわけで、①から③の原因があるかもしれないです。 そんなときには、 ①には ことばの実況中継 ②には まねのレッスン ③には 向き合ってその都度教えていく が必要です!! 具体的なところは、明日書きます♡
-

2024.12.12
よしよしを教えてもらってよかった H様
お母さまから 「よしよしを幼いうちに先生から教えてもらってよかった」 とご感想をいただきました。 その理由をお尋ねすると 「知らなかったら家での対応が変わってくる」 「学校でやる気に満ちている(いろいろあるけど) ということは、甘えが育っていて傷ついても回復できているということ」 「学校でも先生に相談できているようで 他人への信頼ができているってこと」 とのことでした!! よかったです♡ お子様も、自分との付き合い方を学びたいって思ってきていて 自己コントロールを学ぶ感じ。 すごいね!! この変化の陰には もちろん親ごさんが子どものネガティブな気持ちに付き合い よしよしして慰めるということを たくさんしてくれたからです。 一緒にがっばりましたね!! ネガティブな気持ちに寄り添うのは、まぁまぁ難しいですもんね。 ありがとうございました。 次の課題は、本格的な怒りのコントロール。 気持ちを吐くのをがんばりましょう! あなたを応援しています。 発達支援教室クローバーで 一度体験してみてください。
-

2024.12.11
新しいことは腑に落ちるまで導入したくない
言い方にしても やり方にしても 新しいものは受け入れ難し!! の人々が自閉症スペクトラムです。 受け入れ難しなのですが 素直になってくると がんばって受け入れようとする姿が見られてきます。 それが、 のたうちまわったり 踊ってみたり(不適切に) 歌ってみたり(不適切に) 椅子の上で落ちそうになってみたり です(笑) これらのあと、注意深く観察してみて下さい。 たいがい、新しいことを少しだけでも受け入れています♡ かわいいのです。
-

2024.12.10
言い訳、しちゃいたいとき
言い訳って、嫌われますよね。 でも、したいですよね。 だって、こころが痛い、耐えられないから。 でもここは 潔くやっちゃったね、てへ♡ がよいですね。 言い訳したいときって、自分のせいだと思いたくないとき だと思うのです。 わざとではないし、ってとこありますよね。 そんなときに、やっちゃったことの意味を変えると いいのかなって思います。 確かに失敗かもしれないけど その失敗は大したことないの! そして、その失敗は ゆるされるの! だから大丈夫!! この信頼があれば 言い訳から卒業できるかも。 大丈夫って教えてあげてね。 あなたにも、子どもにも。
-

2024.12.10
したいことをどんどんしましょう
人生は練習です。 練習したことがどんどん卓越して、才能になって行きます。 また 苦手なことは【成果が上がらない】ことがわかっています。 ということは、どれだけ時間をかけてもダメってこと。 だから、心理学では【苦手なことは積極的に後回ししよう】 となっております。 だから、これはあなたの人生にも、発達支援にも子育てにもあてはまりますが 【したいこと】【得意なこと】をたくさんして練習したほうが 人生ではお得だということです。 それがお仕事になる日が来るかもしれません! 今日から考えを変えて マルチに活躍ではなく したいことで活躍できる自分にしていきましょう!! ぜひ子育てにもお役立てください。
-

2024.09.04
問題行動の時には反省させず教えるのが吉
そもそも、問題行動は「甘えさせて」の訴えなので 叱ったり反省させるのは、子どもにとってダメージが大きいです。 ダメージが大きくて、傷となり、将来により大きな問題を起こす可能性が示唆されています。 (犯罪心理学) つい、しかったり、もうしないって言わせたりしがちですが それは害なのでやめましょう。 ではどうするかというと、 甘えたい気持ちを受け止めて、かつ教えましょう! よしよしして、気持ちを受け止め、好ましい方法を教えるのです。 アマトレが有効です。 アマトレセミナーで学んでみてください。 お会いできるのを楽しみにしております。
-

2024.09.03
お友達のおもちゃを奪う!どうしたらいい?
ほしい!と思ったら即行動、そしてお友達のおもちゃを奪う。 そんな子、多いですね。 どうしたらいいのでしょう? そんなときには、こう教えましょう! 1 まずは大人で練習。奪おうとしたら、おもちゃから手を離さない。 2 「貸して」と教える(させる)。貸し手と言えたら、「いいよ」と返す。 まだおもちゃから手を離さない。 3 子どもに「ありがとう」と言われたら(言わせたら)おもちゃをあげる。 これで、だいぶ定着していきます。 子ども相手だと、必要ないと感じているのか長く時間はかかります。 園の先生などに手伝ってもらって、定着させていけたらと思います。 ほかの子どもで「貸して」といわせるときには おもちゃを奪いそうなときや奪っちゃったときに遭遇したら教えましょう。 そんなときには、 奪う前なら「貸して」と言わせましょう。 奪っちゃった後なら、「奪うのは悲しいね、返しましょう。」→「貸してと言おう」→貸してを言わせる、がよいでしょう。 しかし、貸したくないときもあると思いますので、ちょっと複雑になります。 相手の子が嫌な時には、「今は嫌」と言わせる必要と 嫌と言われたときの子どものネガティブな気持ちを受け止める支援が必要になります。 複雑なので時間はかかりますが、そのうちに定着します。 詳しくお知りになりたい場合には 発達支援講座入門編がおすすめです♡ お会いできるのを楽しみにしております。