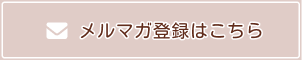お役立ち情報INFORMATION
-

2025.02.06
大人の発達障害 会話の支援
大人の発達障害 自閉症スペクトラムの方から相談がありました。 就労支援の支援者の方にも「あなたは何が言いたいの?」と言われてしまい どうしていいかわからないとのことです。 実は、会話ができるようになるまでにはいくつかの発達が必要なのです。 ・語彙力 ・気持ちに気づく力 ・気持ちを伝える力 ・人への信頼感(伝えても大丈夫と思える) などです。 その発達には、実は【甘え発達】が大切です。 信頼は、その基本で【基本的信頼】の発達があってこそです。 甘えの発達は一人でもできます。 その方法は、個々人で違います。 もし必要なら、お声をおかけください。 https://hattatsu-clover.com/contact/ https://youtu.be/YLuXoDLwIo8
-

2025.02.06
成功と失敗について 発達支援の心理学
https://youtu.be/veF0OZdYW8M
-

2025.02.06
小学校入学準備への支援
https://youtu.be/XwFbdF_JsZI
-

2025.02.06
トイレの自立 支援
https://youtu.be/L1IDT3rX1ek
-

2025.02.06
スイッチを押すこだわり への支援
https://youtu.be/FKt6W6P2dUk
-

2025.02.06
みんなと一緒に食べられないときの支援
https://youtu.be/bDcxYKl31gY
-

2025.02.06
高いところに登る 危ないときの支援
https://youtu.be/EB60wJoxA4A
-

2025.02.06
叩くときの支援
https://youtu.be/bPT9kzQ26vw
-

2025.02.06
こだわりとは
https://youtu.be/xEaXg2wTA_M
-

2025.02.06
こだわりの改善法
https://youtu.be/cO61Lnj6b7w