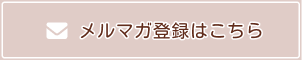お役立ち情報INFORMATION
-

2026.01.05
不登校回復 まとめ
変化の期間まとめ 期間主な変化1〜3ヶ月少し母子分離できる。挨拶ができる4〜5ヶ月登校できる。友達と遊べる。かんしゃくが減る6ヶ月〜1年一人で行動できる。感情コントロールができる2〜3年完全に落ち着く。笑いながら聞き流せる
-

2026.01.04
発語の発達 まとめ
実際に通ってくれた子どもたちの傾向をまとめてみました。 発語に至っては、気持ちを読み取り、サインを教えて発語に結び付ける、このアマトレ®の効果絶大です。 発語改善の傾向まとめ 改善段階目安期間変化の特徴第1段階1か月サインで「やって」が伝えられる言葉が伴い始める第2段階3か月喃語が増える指さしができる自発的にサインを使う第3段階4〜6か月発語が急増オウム返しで語彙が増える「やめて」「ありがとう」など第4段階1年2語文が言える言葉での指示が理解できる第5段階3年3語文でぺらぺら話す会話・しりとりができる
-

2026.01.04
かんしゃくの消失までの道のり まとめ
かんしゃく改善の傾向まとめ 実際に通ってくれた子どもたちの傾向をまとめてみました。 発達支援教室クローバーのアマトレ®だからこそのかんしゃくの消失、前向き思考の獲得だと自負しております。 改善段階目安期間変化の特徴第1段階1か月かんしゃくしながらも達成できる「疲れた」「もうやめたい」と言葉が出始める第2段階3か月暴力・物を投げる行為が減少座っていられる時間が増える第3段階6か月暴言がなくなる深呼吸など自分で落ち着く方法を使える第4段階1年パニック→「ごねる」「怒る」程度に変化気持ちの言葉で表現できる第5段階2年かんしゃく完全消失笑いに変えられるメンタル
-

2026.01.04
やり取り発達段階 まとめ
やり取りの言葉 改善の傾向まとめ 実際に通ってくれていた子どもたちの経過をまとめました。 発達支援教室クローバーのアマトレ®の技術だからこその速さと自負しております。 改善段階目安期間獲得する言葉・変化第1段階1〜2週間自分でできることが増える促されて「疲れた」など言える第2段階1か月「やって」「かして」が言える小さく挨拶ができる第3段階2〜3か月「楽しい」「疲れた」など気持ちの言葉大きな声で挨拶できる自発的にお願いできる第4段階4〜6か月「やめて」「教えて」「させて」など多様なお願い「つらい」「かなしい」「くやしい」など感情の言葉第5段階9か月〜1年「いや」「しません」と断れる会話のやり取りが成立(かして→いいよ→ありがとう)第6段階1年以上「さみしい」「一緒がいい」と気持ちを素直に共感・冗談・相槌ができる
-

2025.12.17
自閉症スペクトラム児の共感発達とポイント
自閉症スペクトラム児の共感発達段階 自閉症スペクトラムのお子さんの共感性は、定型発達のお子さんとは異なる道筋で発達していきます。ここでは、自閉症児特有の共感発達の10段階を、一般保護者向けにわかりやすくまとめました。 はじめに:自閉症児の世界を理解する 自閉症スペクトラムのお子さんにとって、世界は私たちが想像するよりもずっと怖い場所です。 音や光、触覚などの刺激がとても強く感じられる 情報が整理できず、混沌とした世界にいる 何が起こるかわからない恐怖がある そのため、共感の発達も定型発達とは違う順序・ペースで進みます。でも、必ず発達します。焦らず、お子さんのペースに寄り添うことが大切です。 第1段階:混沌の中にいる時期 この時期のようす 人の顔を見ない、目が合わない 呼んでも反応しない 一人で完結しているように見える 抱っこを嫌がることもある お子さんの内側で起きていること 世界のすべてが侵襲的で怖い状態です。人も物も区別がつかず、あらゆる刺激が押し寄せてきます。自分を守るために、外界を遮断しているように見えます。 保護者の方へ 「私を嫌っているのでは」と思わないでください。怖いから縮こまっているのです。無理に目を合わせようとせず、お子さんが安心できる距離感を探りましょう。 第2段階:安心の芽生え この時期のようす 特定の場所や物にこだわる 同じルーティンを好む 親のそばにいることが増える(ただし密着はしない) 大人しくしているが、変化にパニックを起こす お子さんの内側で起きていること 「同じ」であることが安心の源です。予測できることで、ようやく少し世界が怖くなくなります。こだわり行動は自分を守るための大切な方法です。 保護者の方へ こだわりを無理にやめさせないでください。それはお子さんにとっての安心の杖です。まずは「この子のそばにいると安心」という感覚を育てることが第一です。 第3段階:不器用な甘えの始まり この時期のようす 背中からドンと激突してすぐ離れる 近づいてきたかと思うと離れる(接近回避行動) クレーン現象(親の手を使って物を取ろうとする) 親を「道具」のように使う お子さんの内側で起きていること 甘えたい気持ちはあるのに、怖くて素直に甘えられません。「くっつきたい、でも怖い」という葛藤の中にいます。背中から激突するのは、正面から甘えられないからです。 保護者の方へ これは甘えの始まりです。「道具的に使われている」と悲しくならないでください。相手の好意をあてにしているからこそ頼んでいるのです。一瞬の接触を大切にしましょう。 第4段階:「やって」が言える この時期のようす 「やって」「ちょうだい」などの要求が出る サインや身振りで伝えようとする 親の顔を見て確認することがある 少しずつ落ち着いてくる お子さんの内側で起きていること 「この人に頼めば助けてもらえる」という認識が生まれています。これは大きな進歩です。まだ会話ではありませんが、人を頼る第一歩です。 保護者の方へ 「やって」と言えたらすかさず応えましょう。頼んだら応えてもらえたという成功体験が、人への信頼を育てます。言葉が出なくてもサインでOKです。 事例:太郎くん(3歳) 最初は言葉がオウム返しだけでしたが、「やって」を覚えてから自発的にお願いできるようになりました。よく笑うようになり、嬉しいときに声を出すようになりました。 第5段階:人の存在に気づく この時期のようす 親の反応をうかがいながら行動する いたずらをして親の反応を見る 褒められると嬉しそうにする 少しずつ目が合うようになる お子さんの内側で起きていること 「この人は自分とは違う存在だ」ということがわかり始めています。自分と他者の区別(自他の分化)が育ってきた証拠です。 保護者の方へ いたずらは「困らせたい」のではなく、あなたの反応を知りたいのです。大げさに反応してあげましょう。「見てもらえた」という体験が関係を育てます。 第6段階:やりとりの芽生え この時期のようす 「やって」→「いいよ」のやりとりができる 簡単な指示に従える 「かして」「ありがとう」が言える 親のそばに避難してくる お子さんの内側で起きていること やりとりには「役割」があることを理解し始めています。自分が「やって」と言ったら、相手が「いいよ」と返す。このキャッチボールの感覚が育っています。 保護者の方へ 会話の練習は日常の中で自然に行いましょう。「やって」と言えたら「いいよ」と返す。この繰り返しが会話の基礎になります。 事例:花子さん(小1) 最初は言葉がなく、座っていられませんでした。「やって」「いいよ」のやりとりを練習し、2語文が言えるようになりました。「やって」と言ったら「いいよ」が返ってくることを学び、会話の芽が出てきました。 第7段階:感情を言葉にできる この時期のようす 「つらい」「かなしい」「くやしい」が言える 「いや」「やめて」が言える パニックが減り、言葉で伝えようとする 癇癪のあと、親に気持ちをわかってもらおうとする お子さんの内側で起きていること 自分の中の感情に名前をつけることができるようになっています。感情を言葉にできると、パニックに頼らなくてよくなります。 保護者の方へ 感情の言葉を代弁してあげましょう。「悔しかったね」「悲しいね」と言葉をつけてあげることで、お子さんは自分の感情を理解します。叩いてきたときは「つらいね」と受け止めて。 事例:健太くん(小6) 最初はお願いの言葉が言えませんでした。8か月後には「つらい」「かなしい」「くやしい」と言えるようになり、「かして、いいよ、ありがとう」のやりとりができるようになりました。お母さんは「ようやく会話ができた」と涙を流しました。 第8段階:素直な甘えの表現 この時期のようす 正面から「抱っこ」と言える 困ったとき親のところに来る 「一緒にいて」と言える 甘えたいときに甘える お子さんの内側で起きていること 「この人は自分を受け入れてくれる」という信頼が育っています。怖くて近づけなかった人に、素直に甘えられるようになりました。これは大きな成長です。 保護者の方へ この時期の甘えは全力で受け止めてください。「もう大きいのに」と思わないで。自閉症のお子さんは甘えの発達が遅れています。今が甘えを育てる大切な時期です。 事例:翔太くん(小3) 最初は母子分離できず、癇癪がひどく、学校に入れませんでした。4か月後には通学団で登校でき、友達と遊べるようになりました。今では意見も言え、困ったときは言葉で伝えられます。 第9段階:他者の気持ちを想像する この時期のようす 相手が怒っている・悲しいがわかる 「ごめんね」が言える 小さい子や困っている人を気にする 相手の反応を見て行動を変える お子さんの内側で起きていること 「あの人は今こう感じているのかも」と想像できるようになっています。自分の経験を基に、相手の気持ちを推測する力が育ってきました。 保護者の方へ 「あの子は悲しそうだね」「嬉しそうだね」と相手の感情を言葉にして伝えましょう。お子さんは周囲から学ぶことが苦手なので、言葉で教えることが大切です。 第10段階:社会の中での共感 この時期のようす 状況に合わせて行動を調整できる 相手によって態度を変えられる ルールを守って集団活動ができる 困っている人を助けようとする お子さんの内側で起きていること 社会の中での自分の立ち位置がわかり、相手に合わせて行動できるようになっています。これは長い時間をかけて育った力です。 保護者の方へ ここまで来るには長い年月がかかります。でも、必ずここに辿り着けます。焦らず、お子さんのペースを信じてください。 定型発達との違い(まとめ) 定型発達自閉症児生後すぐから人の顔に興味世界が怖くて人を見られない1歳頃から甘えが始まる甘えの始まりが遅れる(個人差大)素直に「抱っこ」と言える背中から激突、接近回避など不器用周囲を見て自然に学ぶ言葉で教えてもらう必要がある感情を自然に獲得感情の言葉を代弁してもらう必要がある 大切なこと 1. 安心が最優先 すべての発達の基盤は安心です。お子さんが「ここは安全だ」「この人といると怖くない」と感じられることが、共感発達の第一歩です。 2. 甘えを育てる 甘えなくして共感は育ちません。不器用な甘えも、背中からの激突も、すべて甘えの芽です。大切に受け止めてください。 3. 代弁する お子さんは自分の気持ちを言葉にするのが苦手です。「悔しいね」「嬉しいね」と代弁してあげることで、感情の理解が進みます。 4. 教える 自閉症のお子さんは周囲を見て自然に学ぶことが苦手です。社会的な行動は言葉で教える必要があります。叱るのではなく、正しい方法を教えましょう。 5. 焦らない 杉山先生の研究によれば、自閉症児が母親に素直に甘えるようになるのは小学校中学年以降のことも珍しくありません。発達には時間がかかります。でも、必ず発達します。 発達の目安(まとめ表) 段階状態キーワード1混沌の中にいる目が合わない、一人で完結2安心の芽生えこだわり、ルーティン3不器用な甘え背中から激突、接近回避4「やって」が言える要求、サイン5人の存在に気づく反応をうかがう、目が合う6やりとりの芽生えかして・いいよ・ありがとう7感情を言葉につらい、かなしい、くやしい8素直な甘え抱っこ、一緒にいて9他者の気持ちを想像ごめんね、相手を気にする10社会の中での共感状況に合わせる、助ける おわりに 自閉症のお子さんの共感発達は、定型発達のお子さんとは道筋が違います。でも、必ず発達します。 大切なのは、お子さんの「世界が怖い」という感覚を理解し、安心を与え続けることです。安心があれば、甘えが育ち、甘えが育てば、相手の気持ちを感じる力が育ちます。 お子さんのペースを信じて、一緒に歩んでいきましょう。 参考文献 修士論文「自閉症児とその母親への子育て支援方法」 土居健郎『甘えの構造』 小林隆児『自閉症の関係発達臨床』 杉山登志郎『発達障害の子どもたち』
-

2025.12.17
健常な共感の発達とポイント
共感の発達段階 子どもの共感性は、段階を経て発達していきます。以下に、一般保護者向けにわかりやすくまとめた10段階の発達表を示します。 第1段階:表情への気づき(0〜3か月) この時期のようす 人の顔をじっと見つめる あやされると笑う 親の声を聞くと動きが止まる ポイント 赤ちゃんは生まれてすぐから、人の顔に興味を持っています。まだ「相手の気持ち」はわかりませんが、人と関わる準備が始まっている時期です。たくさん顔を見せて話しかけてあげましょう。 第2段階:感情の読み取りの芽生え(4〜6か月) この時期のようす イナイナイバーをすると喜ぶ 親しみの顔と、怒りの顔の違いがわかる 歌うとじっと聞き入り、目や口を見つめる ポイント 表情から「なんだか違う」と感じ取れるようになってきます。楽しい顔・怖い顔の区別ができるようになる大切な時期です。笑顔でたくさん関わりましょう。 第3段階:相手の感情に反応する(7〜12か月) この時期のようす 親の話し方で、感情を聞き分ける(禁止など) 拍手などの身振りをまねる 親の話しかけに応えようとする 褒められると同じことを繰り返す おもちゃを取り上げられると不快をあらわす ポイント 親の「嬉しい」「ダメ」などの感情を声や表情から読み取れるようになります。褒められると喜び、また同じことをしようとします。相手に合わせようとする心の芽が育ち始めています。 第4段階:相手の反応をうかがう(1歳〜1歳半) この時期のようす 親の反応をうかがいながら、いたずらをする 難しいことに出会うと、助けを求める 簡単な手伝いをしようとする 「やって」と頼める ポイント 「これをしたらお母さんはどうするかな?」と相手の反応を予測して行動できるようになります。お手伝いをしようとするのも、相手に喜んでもらいたい気持ちのあらわれです。 第5段階:自分と相手は違うことがわかる(1歳半〜2歳) この時期のようす 友だちにおもちゃを貸してあげる 「熱い」「冷たい」「怖い」がわかる 自分より年下の子どもにちょっかいを出す 友だちと手をつなげる ポイント 「自分」と「相手」が別々の存在だと気づき始めます。だからこそ**「貸してあげる」ができる**ようになります。また、自分の感覚を言葉で表現できるようになり、共感の基盤ができてきます。 第6段階:相手の気持ちを想像し始める(2〜3歳) この時期のようす 友だちとケンカをすると親に言いつけにくる 買ってほしい物があっても、言い聞かせれば我慢できる ままごと遊びで何かの役を演じる 「よい・悪い」がわかる ポイント ごっこ遊びを通して、他の人の立場になってみる練習が始まります。「お母さん役」「赤ちゃん役」を演じることで、相手の気持ちを想像する力が育ちます。我慢ができるようになるのも、「相手の言うことを理解した」からです。 第7段階:社会的な気持ちの理解(3〜4歳) この時期のようす 自分が作ったものを見せたがる 褒められると、もっと褒められようとする 順番を自分から待てる 知らない人に注意されたらすぐにやめる 「くやしい」「約束」がわかる ポイント **「認めてほしい」「褒めてほしい」**という気持ちが強くなります。これは相手がどう思うかを意識している証拠です。また、順番を待てるのは、相手にも順番があると理解できるからです。「くやしい」という複雑な感情もわかるようになってきます。 第8段階:思いやりの行動(4〜6歳) この時期のようす 小さい子の世話をする 表情から気持ちを読み取る 場面を想像して気持ちを言葉で表現できる 「親切」「勝ち・負け」がわかる グループの中で妥協しながら遊ぶ ポイント 思いやりの行動が具体的にできるようになります。「あの子は悲しそう」「困っているみたい」と、相手の内面を読み取って助けようとします。グループ遊びの中で譲り合う経験も、共感力を育てます。 第9段階:相手の立場に立って考える(6〜10歳) この時期のようす かわいそうな話を聞くと涙ぐむ 相手の立場や気持ちを考え、困ることや無理な要求をしない 年下の子どもの世話や子守を任せられる 幼児や老人をいたわることができる 「勇気」「無駄」がわかる ポイント 物語を聞いて泣けるのは、登場人物の気持ちを自分のことのように感じられるからです。これが真の共感です。「相手が困るからやめよう」と考えて行動できるようになり、弱い立場の人をいたわる心も育ちます。 第10段階:成熟した共感(10歳以上) この時期のようす 相手の立場を考えて話すことができる 目上の人には丁寧な言葉が使える 相手によって言葉遣いを変えられる 新聞やニュースに関心を持つ グループで計画を立てて実行できる ポイント 相手の立場や状況に合わせて言葉や態度を調整できるようになります。これは高度な共感力であり、社会で生きていく上での大切な力です。社会的な出来事にも関心を持ち、自分とは違う立場の人にも思いを馳せられるようになります。 共感を育てるために大切なこと 1. 安心できる関係をつくる 子どもは安心できる関係の中で相手の気持ちを感じ取る力を育てます。まずは親子の間で「わかってもらえた」という体験をたくさん積み重ねましょう。 2. 子どもの気持ちを言葉にしてあげる 「悲しかったね」「嬉しいね」と代弁してあげることで、子どもは自分の感情を理解し、やがて相手の感情も理解できるようになります。 3. ごっこ遊びを楽しむ ままごとやヒーローごっこなど、役になりきる遊びは共感力を育てる最高の練習です。一緒に遊んであげましょう。 4. 絵本の読み聞かせをする 登場人物の気持ちについて「どう思う?」と一緒に考えることで、他者の視点を取る練習ができます。 5. 焦らず見守る 共感性の発達には個人差があります。周りと比べず、その子のペースを大切にしましょう。 発達の目安(まとめ表) 段階年齢の目安キーワード10〜3か月人の顔に興味を持つ24〜6か月表情の違いに気づく37〜12か月親の感情を読み取る41歳〜1歳半相手の反応を予測する51歳半〜2歳自分と相手は違うとわかる62〜3歳ごっこ遊びで役を演じる73〜4歳認めてほしい気持ちが育つ84〜6歳思いやりの行動ができる96〜10歳相手の立場に立てる1010歳以上相手に合わせて調整できる 注意: これらは目安であり、お子さんによって発達のペースは異なります。「できない」ことを心配するより、日々の関わりの中で少しずつ育てていくことが大切です。 参考資料 KIDS 乳幼児発達スケール S-M社会生活能力検査
-

2025.11.18
今日から始められる!5つの実践方法
今日から始められる!5つの実践方法 最後に、今日から始められる実践方法をまとめますね。 1. 気持ちの言葉を返す - 「痛かったね」「悔しいね」「嬉しいね」 - 1日10回を目標に 完璧を目指さなくて大丈夫。 できるときに、できる範囲で。 それだけで十分です。 2. ことばの実況中継 - 「積み木、持ったね」「お水、飲んだね」 - お子さんの行動を見ながら、その場で言葉にする 地味に見えますが、とても効果的です。 3. アマトレの3ステップ - ①気持ちをわかる → ②よしよしする → ③適切な方法を教える - 癇癪が起きたときに実践 最初は難しく感じるかもしれません。 でも、何度も繰り返すうちに、自然とできるようになります。 4. 気持ちカードを作る - 画用紙に表情を描く - 「嬉しい」「悲しい」「怒り」の3つから始める 週末に、お子さんと一緒に作るのも楽しいですよ♪ ### 5. 一緒に遊ぶ時間を作る - 1日10分でOK - お子さんの好きな遊びに付き合う - 共感のやり取りを大切に 忙しいママも多いと思います。 でも、1日10分だけ、スマホを置いて、お子さんと向き合う時間を作ってみてください。 それだけで、お子さんは「ママは私を見てくれている」と感じられるんです。 続けるコツ 完璧を目指さない: できる範囲で、できるときに。 それだけで十分です。 100点満点じゃなくていいんです。 60点でも、50点でも、続けることが大切。 小さな変化を喜ぶ: 「今日、『嬉しい』って言えた!」 「今日、癇癪が少なかった!」 そんな小さな変化を、ママ自身が喜びましょう。 お子さんも、ママの喜ぶ顔を見ると、嬉しくなるんです。 記録をつける: カレンダーに「今日できたこと」を書く。 ・「取って」と言えた ・癇癪がなかった ・お友達におもちゃを渡せた こんな風に、小さなことでもいいので記録してみてください。 後で見返すと、お子さんの成長が見えて、励みになります♪ そして、「こんなに成長したんだ!」と実感できます。 「わからない」が「わかる」に変わるとき ここまで、長いお話にお付き合いいただき、本当にありがとうございます♪ 最後に、お伝えしたいことがあります。 お子さんが人の気持ちを理解できるようになるまでには、時間がかかります。 でも、確実に変化していきます。 私は、20年以上、たくさんのお子さんとママを見てきました。 そして、すべての子が、必ず変化していくことを知っています。 変化の目安 個人差はありますが、こんな目安があります。 - 1か月*: ママの顔を見るようになる、癇癪が減る - 3か月後: 気持ちの言葉が出てくる、語彙が増える - 6か月後: お友達の気持ちに気づき始める - 1年後: 感情をコントロールできるようになる 早い子もいれば、時間がかかる子もいます。 でも、必ず変化していきます。 最も大切なこと お子さんが変わるために、最も大切なのは、 「ママが子どもの気持ちを理解しようとすること」 そして、 「ママ自身が自分を責めず、優しくすること」 なんです。 「私の育て方が悪いのかな」 「私が至らないから、この子は…」 そう自分を責めないでください。 あなたは、すでに十分頑張っています。 毎日、お子さんのために一生懸命です。 それだけで、素晴らしいママなんです。 だから、まずはママ自身に優しくしてあげてください。 「私、よく頑張ってる」 「私、えらい」 そう自分に言ってあげてください。 ママが自分に優しくできると、お子さんにも優しくできます。 ママが笑顔でいると、お子さんも笑顔になります。 「わからない」が「わかる」に変わると、子育ては驚くほど楽になります。 そして何より、お子さんがいきいきと変化していきます。 一緒に、お子さんの成長を喜びましょう♪ 笑顔で過ごせる日々が増えていきますように。 心から応援しています! お子さんの発達段階に合わせて、オーダーメイドの支援を提供します。 週1回のセッションと、連絡帳での毎日のやりとりで、お子さんの成長をサポートします。 1か月で変化を実感される方がほとんどです。 教室の詳細はこちら。 http://hattatsu-clover.com/course 体験セッションも受け付けています。 お気軽にお問い合わせください♪ https://hattatsu-clover.com/inquiry
-

2025.11.08
【言葉ゼロの3歳児】発達障害・発達支援 気持ちの理解から
1年で「ありがとう」「ごめんなさい」が言えるようになった軌跡 言葉がない、走り回る、目が合わない そんな3歳児が1年後にはアイコンタクトしながら挨拶できるように 「この子、いつか話せるようになるのかしら…」 3歳になっても言葉がない。 呼んでも振り向かない。 目も合わない。 お子さんの発達に不安を感じているあなたへ。 今日は、同じ不安を抱えていた太郎くん(3歳)のお母さんの体験をお伝えします。 最初の太郎くんの状態 - 言葉がない - 訴えるサインもない - 走り回る - 言葉が通じない - 目が合わない 小児科の先生からは「様子を見ましょう」と言われ 児童発達支援にも通っていましたが、目立った変化はありませんでした。 お母さんは、焦りと不安で押しつぶされそうでした。 1か月後:小さな変化 クローバーでは、Miくんの動きに合わせて必要なやり取りを教え、言葉を浴びせていきました。 Miくんは本を出すのが大好き。 出したら、必ず片付けさせる。 そして、「やって」をサインで覚えさせました。 Miくんのサインは、2回だったり3回だったりしましたが、 人ではなく、モノの方に向けてサインをしていました。 これは、「人」への意識がまだ弱いことを意味しています。 3か月後:目が合うようになった そして3か月後。 太郎くんに大きな変化が起きました。 - 指さしをするようになった(少し曲がっているが) - 一緒に遊ぶときに目が合うようになってきた - 喃語がとても増えた 特に、目が合うようになった**ことは、大きな成長です。 これは、「人への意識」が芽生えた**証拠なのです。 6か月後:共感が育ってきた 6か月後には、さらなる変化が。 - お願いの時に目を合わせられるようになった - 楽しいときも目を合わせる - 「やって」のときに目が合う、こちらを見る - どうしてもすぐにしたいときには、モノのほうを見て「やって」をする(これは自然なこと) - 「やめて」も教え、少しずつできるようになった お母さんは言いました。 「息子が私を見てくれる。それだけで、涙が出るほど嬉しいんです」 1年後:言葉の理解が進んだ そして1年後。 - 言葉の指示をだいたいわかっている - サインで「やって」「やめて」を目を見て表せる - 挨拶を目を合わせてできる - 共感したい気持ちが出てきている さらに、現在(2025年10月)では: - 言っていることの理解がある - 何か言おうとするところがある - まねをするようになってきた - 自ら求めてアンパンマンなどの手遊び歌をしていた 太郎くんは、確実に「人とつながる喜び」を感じ始めています。 なぜ、こんな変化が起きたのか? 多くの療育では、「訓練」という形で言葉を教えます。 しかし、クローバーでは違います。 お子さんの「今、したいこと」に寄り添い その瞬間に必要な言葉とやり取りを教えるのです。 太郎くんにとって、本を出すことは「楽しい」こと。 その楽しい瞬間に、「やって」「ありがとう」「どうぞ」などの言葉を浴びせる。 すると、お子さんは「人とやり取りするのは楽しい」と感じるようになるのです。 発達には順番がある 言葉の発達には、実は順番があります。 1. 人への意識(目が合う) 2. 共感の育ち(楽しいことを共有したい) 3. サイン・ジェスチャー 4. 発語 5. 2語文 6. 会話 多くの親御さんは、「早く話してほしい」と焦ります。 でも、土台(人への意識、共感)がないまま言葉だけ教えても、定着しないのです。 クローバーでは、この順番を大切にしながら、お子さんの発達を促していきます。 あなたのお子さんも変われます もし、あなたのお子さんが: - 言葉がない - 目が合わない - 呼んでも振り向かない - 一人の世界にいるように見える そんな状態でも、大丈夫です。 適切な関わり方で、必ず「人とつながる喜び」を感じるようになります。 今すぐ、相談へ 発達支援教室クローバーでは、相談を実施しています。 お子さんの今の発達段階を丁寧に見極め、最適なサポート方法をご提案します。 【相談は月10名様限定】 「この子、いつか話せるようになるのかしら…」 そんな不安を抱えているなら、今すぐご相談ください。 お子さんの「言葉」と「笑顔」は、必ず花開きます。 ▼無料相談のお申し込みはこちら▼ [お問い合わせフォームへ]
-

2025.11.06
【衝撃】「絶対できない」が口癖だった小1「きっとできる」へ 気持ちの変化
暴言、暴力、物を投げるそんな小1男児が半年で深呼吸しながら課題に取り組めるように 「どうせできない」 「絶対無理」 「やりたくない!」 お子さんのネガティブな言葉に、心が折れそうになっていませんか? 今日は、幼稚園時代から暴言・暴力がひどかった太郎くんの変化をお伝えします。 最初の太郎くんの状態(幼稚園時代から) - 暴言と暴力 - 気に入らないと暴言と暴力 - 投げやり - 奇声 - 目の動きが悪い - 形の認識が弱い お母さんは、毎回のレッスンで謝ってばかりでした。 「すみません、またモノを投げてしまって…」 「暴言がひどくて、本当に申し訳ありません…」 でも、お母さんが謝る必要はないのです。 1か月後:怒りながらも達成 クローバーでのセッションを始めて1か月。 太郎くんは、怒りながらも少しずつ達成できるようになりました。 - 奇声や暴言はまだある - モノを投げることもある - でも、形の認識が少し上がった - 目の動きも少し良くなった 「怒りながらも、できた」 これが、大事なポイントです。 3か月後:暴力が減った 3か月後には、さらなる変化が。 - 怒るが、達成できるようになった - 怒った時は暴言はまだある - でも、暴力、ものを投げるのは治まってきた - 「ドンマイ」を嫌がる(過去に嫌な体験があったよう) - 最後までできるようになってきた - 「絶対できない」と嫌がったお手玉の練習を自発的にするようになった この「自発的にする」という変化は、とても大きいことです。 6か月後:まるで別人 そして6か月後。 お母さんは、涙を流しながら言いました。 「先生、息子が変わったんです。まるで別人みたいに」 太郎くんに起きた変化: - 深呼吸をしながら続けられる - 暴言なし - ドンマイもOKに - モノを投げない(投げる真似だけ) - 「今度こそ」とできるようになった - 「絶対できない」と言っていたお手玉を「きっとできる」とするようになった 「絶対できない」から「きっとできる」へ。 この言葉の変化は太郎くんの心の変化そのものです。 なぜ、暴言が減ったのか? 多くの方は、「暴言を止めさせよう」と考えます。 でも、クローバーでは違うアプローチをとります。 「できた」体験を積み重ねる。 お子さんが暴言を吐くのは、「どうせできない」という思い込みがあるから。 過去に何度も失敗し、傷ついた経験があるから。 だから、小さな「できた」を積み重ねることで、自己肯定感を育てるのです。 すると、自然と暴言は減っていきます。 「深呼吸」という魔法 6か月後のYくんは、困った時に「深呼吸」をするようになりました。 これは、私たちが教えた「自己調整」の方法です。 イライラした時、 できない時、 投げ出したくなった時、 「深呼吸してみよう」 これだけで、子どもは落ち着きを取り戻せます。 そして、もう一度チャレンジできるのです。 あなたのお子さんも変われます もし、あなたのお子さんが: - 「どうせできない」が口癖 - すぐに暴言を吐く - モノを投げる - 最後までやり遂げられない そんな状態でも、大丈夫です。 「できた」体験を積み重ねることで、必ず自己肯定感は育ちます。 今すぐ、相談へ 発達支援教室クローバーでは、相談を実施しています。 お子さんの「自己肯定感」を育てる方法を、一緒に考えましょう。 【相談は月10名様限定】 「この子、いつもネガティブで心配…」 「暴言がひどくて、将来が不安…」 そんな思いを抱えているなら、今すぐご相談ください。 お子さんの中にある「できる力」を、一緒に引き出しましょう。 ▼無料相談のお申し込みはこちら▼ [お問い合わせフォームへ]
-

2025.11.06
自閉症スペクトラムは「治る」のか?専門家が語る真実と、お子さんの笑顔を取り戻す方法
自閉症スペクトラムは「治る」のか?専門家が語る真実と お子さんの笑顔を取り戻す方法 「この子は、このまま一生…?」 「治るのか、治らないのか、はっきりしてほしい」 「ネットで調べても、情報がバラバラで不安になる」 自閉症スペクトラム(ASD)のお子さんを持つママの、切実な声です。 検索しているあなたも、同じ不安を抱えているのではないでしょうか? もし、このまま何もしなければ どうなると思いますか? お子さんの困りごとは、自然に消えるでしょうか? 保育園や学校での居場所は、自然にできるでしょうか? 将来への不安は、自然に消えるでしょうか? 答えは、NOです。 でも、ここで終わってしまって、いいのでしょうか? 今日は、医学的根拠に基づいた真実と、 お子さんの笑顔を取り戻す具体的な方法をお伝えします。 自閉症スペクトラムは「治る」のか?専門家が語る真実 結論:根本的な「治癒」は現状では不可能。しかし… MSDマニュアルやミネルバクリニックなど、医学的な権威ある情報源によると: 自閉症スペクトラム症(ASD)は、生まれつきの脳の特性による発達障害です。 現在の医学では、根本的に「治す」ことはできません。 この事実を、あなたはどう受け止めますか? 「治らない」という言葉に、恐怖を感じているかもしれません。 「このまま一生、変わらないのか…」と、不安を感じているかもしれません。 でも、ここで終わってしまって、いいのでしょうか? あなたは、お子さんの笑顔が欲しいんですよね? 家族との時間を楽しみたいんですよね? 将来への希望を持ちたいんですよね? 実は、多くのママが、この「治らない」という事実に、最初は絶望を感じます。 でも、その後の「生活の質を向上させることは可能」という希望を知って、 行動を起こしています。 そして、多くのママが、変化を実感しています。 「治す」ではなく「特性と上手に付き合う」という視点 実は、多くのママが気づいていないことがあります。 ASDは「病気」ではなく「特性」なんです。 これは、つまり何を意味するか、わかりますか? 「治す」必要はない。 特性を理解し、適切な環境を整えれば、お子さんは驚くほど生きやすくなる。 専門家の間でも、この考え方が主流になっています。 実際に、多くのお子さんが変化している 発達支援教室クローバーでは、多くのお子さんが、 適切な支援を受けることで、生活の質を大幅に向上させています。 3歳で言葉が出なかったTくんは、1か月で「やって」が言えるようになりました。 幼稚園で噛む・叩くがひどかったSくんは、1年で「ありがとう」を言えるようになりました。 集団になじめなかったHさんは、友達と笑顔で遊べるようになりました。 これらは、すべて「治した」わけではありません。 特性を理解し、適切な環境を整え、段階的に支援した結果です。 実は、多くのママが、同じ悩みを抱えています。 そして、多くのママが、専門家のサポートを受けることで、変化を実感しています。 「一人じゃないんだ」と感じられる、温かい時間が、あなたとお子さんを待っています。 効果的な支援方法:医学的根拠に基づいたアプローチ 1. 応用行動分析(ABA)による段階的な支援 MSDマニュアルによると、治療の中心は行動療法や環境調整などの非薬物療法です。 特に、応用行動分析(ABA)は、特定の認知的、社会的、 または行動的技能を段階的に教えることで、 特性による困難を軽減することができます。 クローバーでも、この手法をベースに、お子さん一人ひとりに合わせた支援を行っています。 2. 環境調整:無理をさせない、適切な環境を整える ミネルバクリニックの情報によると: > 本人の特性を理解し、得意なことを伸ばし、苦手なことに対しては無理をさせず、適切な環境を整えることが重要です。これにより、ASDの方々がより生きやすい社会生活を送ることが可能となります。 これは、家庭でも、保育園でも、学校でも、同じです。 お子さんの特性を理解した環境づくりが、何よりも大切なんです。 3. 周囲の理解とサポート:ママが変わると、お子さんも変わる 学術研究でも明らかになっていることですが: 家族や教育者がASDの特性を理解し、適切な対応を行うことで、 本人の自己肯定感を高め、社会生活への適応を助けることができます。 つまり、ママが正しい知識と方法を学べば、お子さんは必ず変化します。 でも、一人で学ぶのは、大変ですよね? ネットで調べても、情報がバラバラで、何が正しいのかわからない。 専門書を読んでも、難しくて、実践できない。 だからこそ、専門家のサポートを受けることをおすすめします。 専門家が、あなたとお子さんに合わせた、具体的な方法を教えてくれます。 あなたが変われば、お子さんも変わります。 ママが笑顔になれば、お子さんも笑顔になります。 ママが「わかった」と思えると、子育ては驚くほど楽になります。 あなたのお子さんが、笑顔で過ごせるようになるために 今、あなたができること もし、このまま何もしなければ、どうなると思いますか?** 想像してみてください。 1年後、お子さんはどうなっているでしょうか?** - 困りごとが、増えているでしょうか? - 保育園や学校で、居場所がない状態が続いているでしょうか? - 家族の時間が、楽しめなくなっているでしょうか? でも、適切な支援を受ければ、どうなるでしょうか? - お子さんの笑顔が、増えているでしょうか? - 家族の時間が、楽しくなっているでしょうか? - 将来への希望が、見えてきているでしょうか? 答えは、YESです。 1. お子さんの特性を理解する 「治そう」ではなく、「理解しよう」という視点に切り替えてください。 2. 適切な支援方法を学ぶ 応用行動分析(ABA)や環境調整の具体的な方法を学ぶことで、 お子さんの困りごとを軽減できます。 でも、何から始めればいいのか、わからない…そんなあなたへ 「情報はわかった。でも、実際に何をすればいいのか、わからない」 そう思っているママも、多いのではないでしょうか? 実は、多くのママが、同じ悩みを抱えています。 でも、多くのママが、専門家のサポートを受けることで、変化を実感しています。 あなたは、今、何をすべきか、わかりますか? あなたは、今、何をすべきか、わかりますよね? 一人で悩むのではなく、専門家に相談する勇気を持ってみませんか? まずは、相談してみませんか? 発達支援教室クローバーでは、相談を実施しています。 「うちの子、本当に大丈夫なのかな?」 「このままでいいのかな?」 「何かできることはないかな?」 そんな不安や疑問を、専門家に相談してみませんか? 一人で抱え込まないでください。 あなたは、もう十分頑張っています。 だから、専門家に頼る勇気を持ってみませんか? --- 相談の内容 - お子さんの発達段階の確認 - 現在の困りごとの整理 - 今すぐできる具体的な対応方法 - 必要に応じた支援プランの提案 もちろん、無理な勧誘は一切ありません。 あなたとお子さんにとって、本当に必要なことだけをお伝えします。 最後に:あなたの決断が、お子さんの未来を変える 「自閉症スペクトラムは治るのか?」 この質問への答えは、「根本的な治癒は難しい。」 でも、生活の質を向上させることは十分に可能」です。 そして、その可能性を広げるのは、あなた自身の決断です。 お子さんは、今、あなたのサポートを待っています。 適切な支援を受けることで、お子さんの笑顔は、必ず増えます。 家族の時間は、必ず楽しくなります。 将来への希望は、必ず見えてきます。 まずは、一歩を踏み出してみませんか? お問い合わせ 心から応援しています。